はじめに
日本語って、普段なんとなく使っている言葉でも、実は本来の意味と逆に覚えられているものがたくさんあります。
しかもニュースやドラマでも堂々と誤用されていることもあって、いつの間にか「え、それ違ったの!?」と驚かされることも。
そこで今回は、間違いやすい日本語をクイズ形式で9問出題します!
記事の後半に答えと解説がありますので、ぜひ挑戦してみてください。
クイズ編
Q1.「確信犯」の正しい意味はどっち?
A. 悪いと分かっていながらする犯罪
B. 道徳的に正しいと信じて行う犯罪
Q2.「情けは人のためならず」の意味は?
A. 人のためにならないから、親切にしないほうがよい
B. 人に親切にすると、巡り巡って自分に返ってくる
Q3.「失笑」するときはどんなとき?
A. 思わず吹き出して笑うとき
B. あきれて笑うとき
Q4.「煮詰まる」状況とは?
A. 行き詰まって進まない状態
B. 検討が進んで結論に近づく状態
Q5.「やおら立ち上がる」とは?
A. ゆっくり立ち上がる
B. 急に立ち上がる
Q6.「憮然(ぶぜん)とする」の意味は?
A. 失望してぼんやりするさま
B. 怒っているさま
Q7.「姑息な手段」とは?
A. 卑怯な手段
B. 一時しのぎの手段
Q8.「敷居が高い店」とはどんな店?
A. 高級すぎて入りにくい店
B. 不義理などで行きにくい店
Q9.「役不足」とはどんな状態?
A. 役目が軽すぎて物足りない状態
B. 力量が足りない状態
正解と解説編
Q1. 「確信犯」
A. 悪いと分かっていながらする犯罪
B. 道徳的に正しいと信じて行う犯罪
→ B
本来の意味
宗教や政治・思想的な「信念」に基づいて行う犯罪。
本人は「これは正しい」と信じているので、悪いことをしている自覚がありません。
誤用の意味
「悪いと分かっていながら、わざとやる人」。
なぜ誤用が広まった?
テレビのニュースやワイドショーで「芸能人の不祥事=確信犯」と報じられたのが原因。
「確信=悪事を確信」と勘違いされ、一般化しました。
👉 会話での注意:
日常会話では誤用でも通じますが、論文・記事などフォーマルな場面では本来の意味で使うのが安全です。
Q2. 「情けは人のためならず」
A. 人のためにならないから、親切にしないほうがよい
B. 人に親切にすると、巡り巡って自分に返ってくる
→ B
本来の意味
「人に親切にすると、いずれ自分に返ってくる」という教え。
「ならず」は古典的な表現で「〜のためになる」の意味。
誤用の意味
「他人のためにならないから、親切は無駄」。真逆!
なぜ誤用が広まった?
現代人が「〜ならず」を“〜ではない”と解釈してしまったため。
古典的な表現を知らない世代に誤解が拡散しました。
👉 会話での注意:
人生訓として語られることも多いので、正しく知っていると「お、この人知識あるな」と思われます。
Q3. 「失笑」
A. 思わず吹き出して笑うとき
B. あきれて笑うとき
→ A
本来の意味
「思わず吹き出して笑うこと」。
こらえきれず、プッと笑ってしまうニュアンスです。
誤用の意味
「あざ笑う、バカにして笑う」。
なぜ誤用が広まった?
「失笑=失礼な笑い」と連想されやすい字面が原因。
報道やネットで「失笑ものだ」の表現が誤って使われ、定着してしまいました。
👉 豆知識:
国語辞典の一部では「誤用が広まりすぎて容認」と注記されているケースも。
Q4. 「煮詰まる」
A. 行き詰まって進まない状態
B. 検討が進んで結論に近づく状態
→ B
本来の意味
料理の煮汁が煮詰まって仕上がるイメージから転じて、議論や検討が進み、結論が近づいている状態。
誤用の意味
「行き詰まって、進展がない」。
なぜ誤用が広まった?
「詰まる」という響きが「行き詰まる」と似ているから。
職場や会議で誤用が繰り返され、逆の意味で浸透しました。
👉 会話での注意:
仕事の場では誤用で使われがちなので、相手の意図を汲み取る柔軟さも必要です。
Q5. 「やおら」
A. ゆっくり立ち上がる
B. 急に立ち上がる
→ A
本来の意味
「ゆっくりと」「そろそろと動作を始める」。
誤用の意味
「急に」「突然」。
なぜ誤用が広まった?
「やおら立ち上がる」と文学作品に出てくると、「急に立った」と誤解しやすい。
日常で使われなくなったため、誤解が定着しました。
👉 豆知識:
古風な表現なので、あえて小説やスピーチで使うと味が出ます。
Q6. 「憮然(ぶぜん)」
A. 失望してぼんやりするさま
B. 怒っているさま
→ A
本来の意味
「がっかりして気力を失い、ぼんやりしている様子」。
誤用の意味
「怒って不満そうにしている」。
なぜ誤用が広まった?
新聞記事などで「憮然とした表情=怒った顔」と誤って使われたのが原因。
音の響きも「ムッとした」に似ているため、誤解が加速しました。
👉 会話での注意:
日常会話では誤用で通じるケースが多いですが、国語辞典的には間違い。
Q7. 「姑息」
A. 卑怯な手段
B. 一時しのぎの手段
→ B
本来の意味
「一時しのぎ」。根本的な解決を避けること。
誤用の意味
「卑怯、ずるい」。
なぜ誤用が広まった?
文章で「姑息な手段」と出てくると「卑怯なやり方」と勘違いされやすい。
マンガやドラマで「姑息=ずるい」と使われ、若い世代にも浸透しました。
👉 豆知識:
医学用語の「姑息手術(延命のための一時的な手術)」は本来の意味どおり。
Q8. 「敷居が高い」
A. 高級すぎて入りにくい店
B. 不義理などで行きにくい店
→ B
本来の意味
「不義理や面目のなさから、その家や場所に行きにくい」。
誤用の意味
「高級すぎて入りにくい」「心理的ハードルが高い」。
なぜ誤用が広まった?
「高い」という言葉のイメージに引っ張られた。
さらにグルメ記事や観光記事で「高級店=敷居が高い」と多用されたため、定着化しました。
👉 会話での注意:
誤用が一般的すぎて、本来の意味を使うと逆に通じにくいこともあります。
Q9. 「役不足」
A. 役目が軽すぎて物足りない状態
B. 力量が足りない状態
→ A
本来の意味
「役目が軽すぎて物足りない」。
つまり「もっと大きな役割を与えてほしい!」というポジティブな意味。
誤用の意味
「力量不足で役目を果たせない」。
なぜ誤用が広まった?
「力不足」と混同されたため。
日常では誤用の方が圧倒的に使われ、本来の意味を知る人が少なくなっています。
👉 豆知識:
実際に会議で「彼は役不足だ」と言うと、褒めてるのか貶してるのか混乱されるので注意。
まとめ
あなたは何問正解できましたか?
私自身、「煮詰まる」や「役不足」は長い間、誤用で覚えてました…。
日本語は時代とともに意味が変わる生き物。
誤用が広まりすぎて辞書に載ることもあります。
でも「本来はこうだったんだよ」と知っているだけで、ちょっとした会話のネタになりますよね。
👉 友達や同僚に「クイズ形式」で出題してみると盛り上がること間違いなし!
他の日本語雑学はこちら↓↓
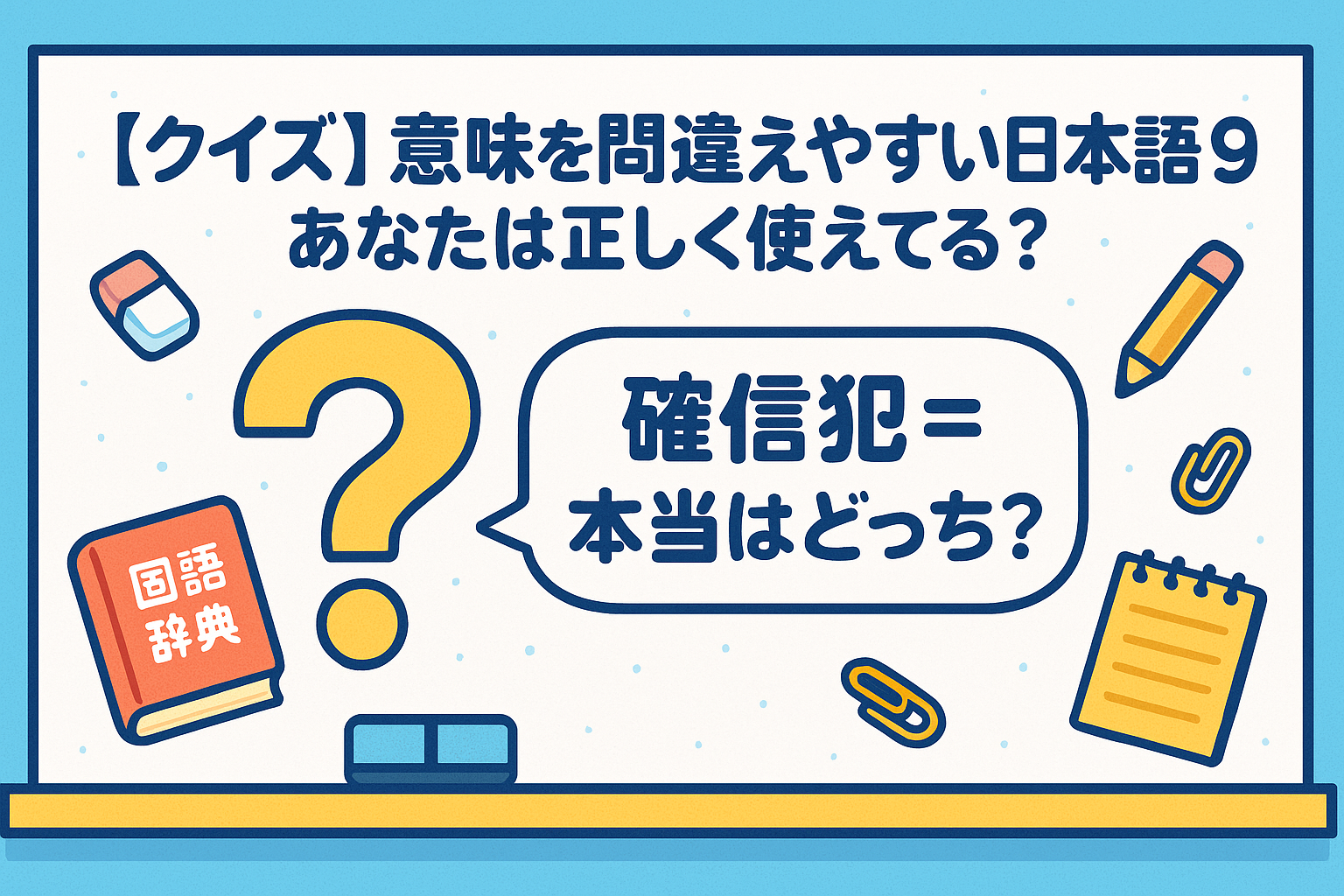
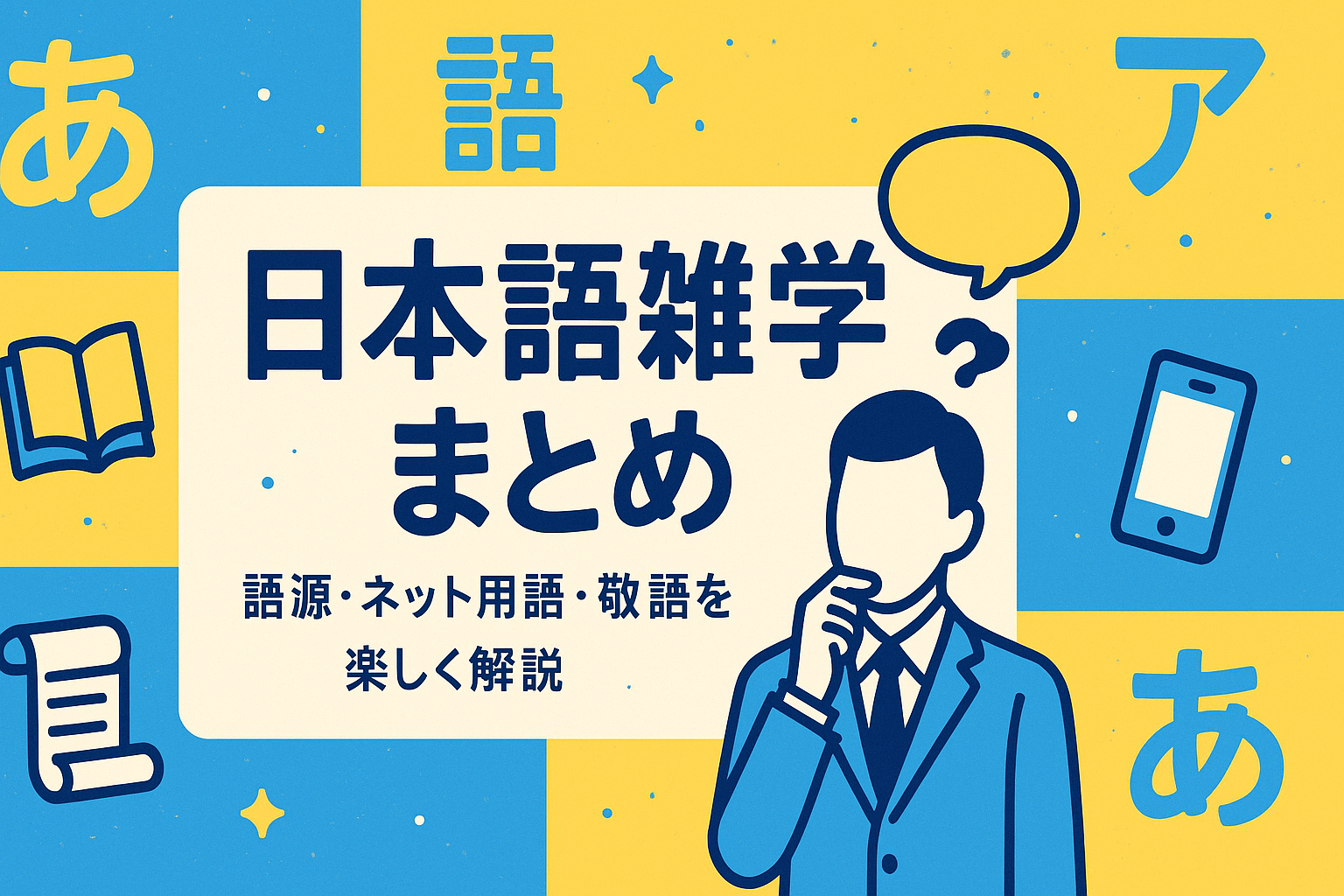

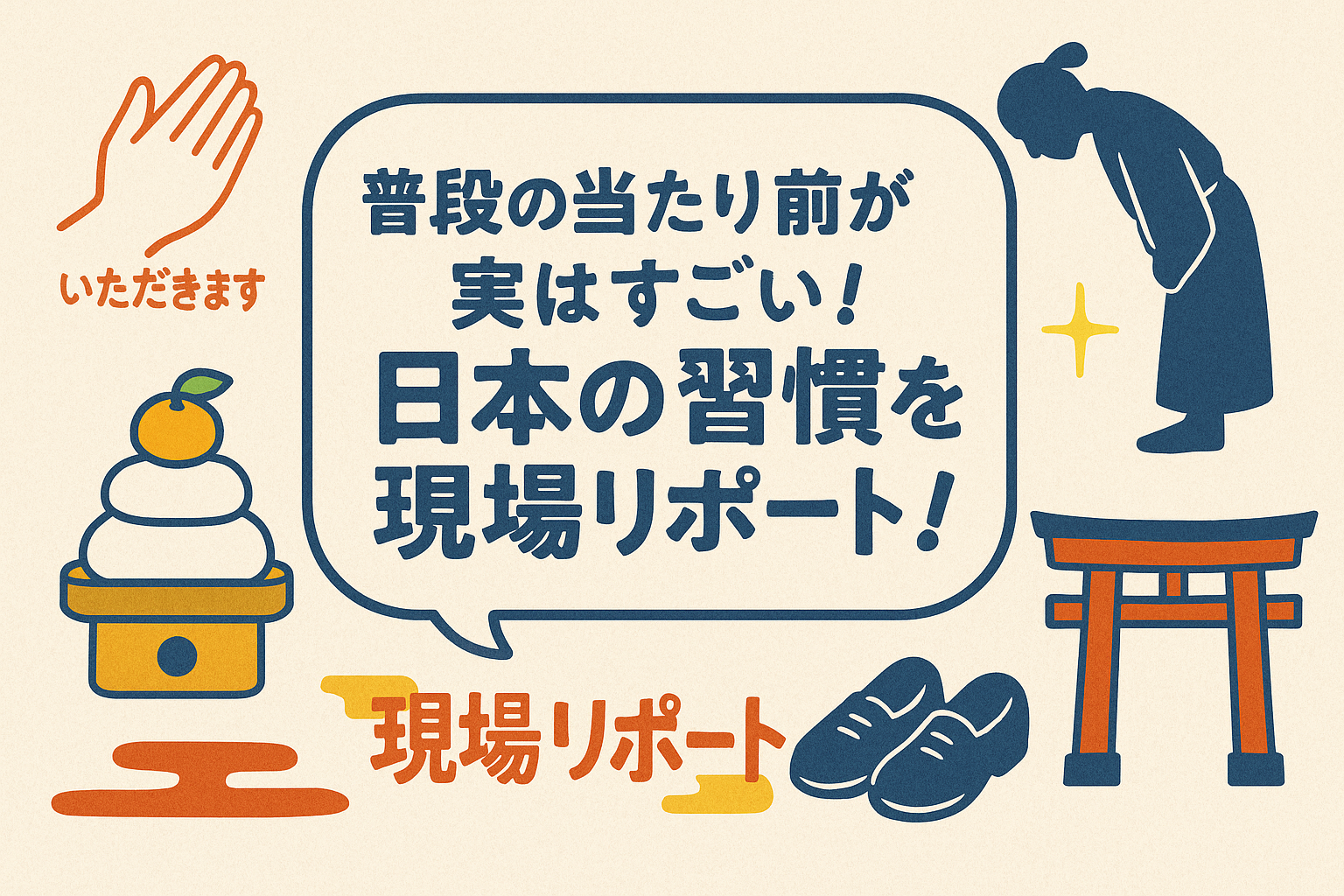
コメント